どうも、中学生です。
一回目の投稿からかなり遅くなってしまいました。特にネタ切れというわけではないのですが、ブログの使い方に四苦八苦していました。(このブログはbloggerで書いています)
そんな話はさておき、今日は日本国憲法の9条について書いていこうと思います。
第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
出典:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#2sho
衆議院のサイトからコピペしてきましたが、始めて見る人からすると、結構びっくりするかもしれません。
だって、向こうから攻めてきても戦えないし。
しかし、そうではありません。
それでは、何でこんなことが憲法に書かれているのか背景を探ってみましょう。
1、背景
第二次世界大戦で日本は敗れ、GHQによって占領されました。敗れたとはいえ、日本は枢軸国の中で最後まで戦い、連合国は日本を恐れてきました。(日露戦争でもロシアに勝っていますしね)
連合国からしたらアジア最強国家だった日本とはもう戦いたくないわけです。そこで大日本帝国を今のもはや別国家である日本に変えてしまおうとなりました。戦前の日本の憲法である大日本帝国憲法には人権保障や三権分立などは記載されていましたが、民主主義とは程遠勝ったのです。(外見的立憲主義)
そこで、GHQは全く新しい憲法を作ることにしました。それが日本国憲法です。日本には無事に平和と民主主義が根付きましたとさ。パチパチパチパチ。
ちなみに、1週間ちょいで作られました
ちなみに、専門家はほとんど関わってません
ちなみに、今年で戦後から78年ですが、その間一回も改正されてません。そんな国は世界中を見ても日本くらいだと思います。
要するに、日本国憲法は確かに日本に平和をもたらしたが、GHQによって割と雑に作られた代物であり、戦後からこんなに月日が経っているのだから改正されて然るべきってことです。
2、自衛隊は軍?
先に結論から言うと軍ではないと言うのが、現在の政府の見解です。
政府の見解もこの78年で結構変わっています。
自衛隊の持つ防衛力を実際に用いることについて、憲法第9条を読むと、国と国との関係における「武力の行使」をすべて禁止しているように見えます。しかし、外国が武力を用いて日本を攻撃してきた場合や、他国に対する攻撃により日本の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、自衛隊が国を守るために武力を行使することが認められています。
ただし、このような場合でも、ほかに適当な手段がなく、必要最小限度の実力行使であることが求められます。相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められません。
これが現在の政府の見解です。初見で見た憲法9条のイメージとはかなり異なる解釈です。もっとわかりやすくするためにも憲法改正は必要なのかなと思います。(軍事的に見ると日本は米、露、中、印に次ぐ世界5位の軍事力を持っており、全然軍事大国ですが)
それでは、過去はどのような見解をがあったのか見ていきましょう。
1、マッカーサーノート(日本国憲法の初期の草案のメモ書きみたいなもの)
- 「日本は、紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
- 「いかなる日本陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利も日本軍には決して与えられない。」
- 現在の政府の解釈とは全然違いますね。当時の憲法学者もほぼこのような解釈です。1項では自衛のための戦争は禁じられていないが、2項で自衛戦争も禁止されたと言う解釈です。
2、吉田内閣の解釈
1946年、当時の首相である吉田茂は国会答弁でこう述べています。
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませんが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」
また同年の別の演説でもこう述べています。
「近年の戦争の多くは国家防衛権の名においておこなわれたることは顕著なる事実であります。故に正当防衛権を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります。...正当防衛を認むることそれ自身が有害であると思うのであります」
つまり、自衛戦争も否定していると言うことですね。
しかし1950年の演説では、「戦争放棄の趣意に徹することは、決して自衛権を放棄するということを意味するのではないのであります」と主張を一転しています。そして、同年に後の自衛隊の前身になる警察予備隊が作られます。
そして、警察予備隊というのは名の通り警察だったのですが、自衛隊になったことで軍事力を持つようになりました。すなわち、警察から軍隊になった訳です。その時の吉田元総理の答弁がこちらです。
「いかなる名称を付けても戦力に至らしめない、という制限の下に軍隊と言い、軍艦と言うことは自由であると思います」
自衛隊は戦力ではない軍隊だからセーフだと言ったのです。もうよくわかりません。
3、鳩山内閣の解釈
そして吉田内閣後の鳩山内閣では、また解釈が変更されます。
「自衛のためならば、必要にして最小限度の限り戦力を持っていい。ただし、紛争解決のため、あるいは侵略戦争のためには、いかなる戦力も持つわけにはいかない」
自衛隊は戦力だけど、侵略するためではなく、自衛のための必要最低限の戦力だからセーフってことです。これが現在の解釈にもかなり影響を与えています。
要するに、この時点で個別的自衛権が認められたということです。
2.5、自衛隊の歩み
解釈は少し離れるのですが、自衛隊にとって大事なことが間に起こったので書かせてもらいます。
佐藤内閣
核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という原則。(ちなみに佐藤元総理は、沖縄に核兵器を配備しようとしていた)
三木内閣
三木内閣では、必要最低限の戦力の整備に必要のお金の金額は、GNP(国民総生産)の1%以内であるという定義付けがされました。(中曽根内閣まで守られます)
それでは、そろそろ政府の解釈に戻りましょう。
3、田中内閣
国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する 武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもつて阻止することが正当化さ れるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第 51 条、日本国との平和条約第5 条(c)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソヴィエ ト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思わ れる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、 当然といわなければならない。
ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有している としても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえる ものであつて許されないとの立場にたつているが、これは次のような考え方に基づくものである。
憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止している が、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、 また、第 13 条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政 の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全う し国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と 安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい 解されない。しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう 自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武 力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不 正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認され るものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にと どまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、 わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加 えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許さ れないといわざるを得ない。
とんでもなく長いのでまとめますと、このようになっています。
1 憲法は、9条2項で戦力保持を禁じている。
↓
2 だが憲法は同時に、前文で「平和のうちに生存する権利」をうたい、第13条では「生命、自由および幸福追求に対する権利」も認めている。
↓
3 従ってこの「生命、自由および幸福追求の権利」が根底から覆されるような時には、必要最小限度のことは認められるはずだ。
↓
4 ならば、個別的自衛権は認められる。だが、まだ自国が攻撃されていない時は「根底から覆される」とまでいえないだろうから、「集団的自衛権の行使」までは認められない。
これまでは、全部個別的自衛権の話でそれは認められるけど集団的自衛権の行使は憲法上認められないよねってことです。
分かりずらくてすみません。
4、1980年の新解釈
政府は、自衛隊の海外派遣について「目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは、憲法上許されないと考えている。これに対し、...目的・任務が武力行使を伴わないものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されないわけではないが、現行自衛隊法上は自衛隊にそのような任務を与えていないので、これに参加することは許されないと考えている」と、自衛隊法を改正すれば武力行使を伴わない自衛隊の海外派遣も可能だという憲法解釈を示しました。
どんどん変わっていきますねw
こうした結果、自衛隊はカンボジア、モザンビーク、ルワンダ、ゴラン高原、東ティモール、イラクなどの国々に派遣されました。
5、安倍内閣
だいぶ月日も流れて、2014年の政府の解釈です。割と最近のことなのでニュースなどで覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
集団的自衛権が容認されました!
でも、なぜか日本の憲法学者の大多数は日本の集団的自衛権に反対なんですよね。理由は憲法9条にああ書いてあるじゃんってことですね。立憲主義に反してるって言われちゃう訳です。
Q どうすれば反対意見がなくなりますか?
A 改正しましょう。
こういうことです。早く改正しましょう。だって、自衛戦争すら否定してた吉田内閣の時と文言が一切変わってないんだもん。
要するに、政府は早く改正しろ。以上。
3、日本って強いの?
一つ気になる点としては、そもそも自衛隊や軍隊がああだこうだ以前に日本の軍事力は強いのでしょうか?
結論:軍事力はそこそこ強いが、外交が弱腰なので舐められがち。
世界でもTOP10には間違いなく入るでしょう。やや陸上自衛隊の人数が少ないかなという印象ですが(15師団)。武器に関しても最新のものが揃っていますし、日米できちんと連携すればまず何らかの戦争に巻き込まれても負けないでしょう。
ただ、外交が異様に下手。そこらへんの詳しい学生の方がまともです。遺憾砲じゃいかんほう。軍事力はそこそこあるんだから、もっと強く出てもいいのに日本人の悪い癖で弱腰になりがちです(筆者はこう言っていますが間違いなくチキンです)。
4、まとめ
今回の記事はいかがだったでしょうか。今後の参考になりますのでコメントで書いていって欲しいです。また、このことについて解説してほしいと言うものやここ間違ってるよ〜と言うものもあったら是非それもコメントでお願いします!(ただしアダルトなものはダメです、流石に)
フォローも是非是非お願いします!
それでは今後ともこのブログをよろしくお願いします!
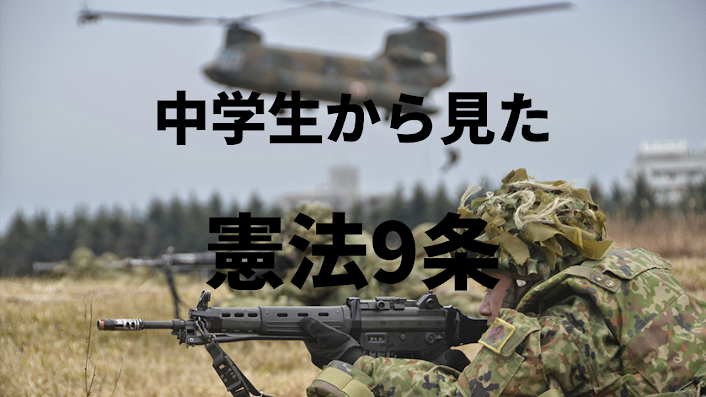


コメント
コメントを投稿